沖縄では、お酒を飲みながら親睦を深める「飲みニケーション」という文化があり、
「お酒」は生活の中に深く根づいています。
結婚式、模合(もあい)、職場の飲み会——どんな場にも泡盛が並び、
「乾杯!!」と笑い合う光景が日常の一部になっています。
けれど、その優しさの裏で、誰かが静かに苦しんでいることもあります。
私は以前付き合っていたアルコール依存の彼との共依存関係を通して、
「飲むことが当たり前」という空気の中に、見えない痛みが潜んでいることを知りました。
このブログでは、私自身の体験を通して感じた
“お酒の怖さ”についてお話しします。
沖縄とお酒、私が気づいた「依存の怖さ」
沖縄は、メディアなどで「酒害の多い地域」と表現されることがあります。
私が20代の頃は、今よりも飲酒運転がもっと多かったように感じます。
しかし、私は子どもの頃から、父や親戚がお酒を飲む姿を日常的に見て育ちました。
社会人になると、友人や職場での飲み会なども重なり、「飲みニケーション」を楽しむ側にいました。
そんな私が、お酒の怖さに気づいたのは——
一人の男性と付き合ったことがきっかけでした。
お酒は、人の心も生活も静かに蝕んでいき、気づいたときには、もう逃れられなくなっている。
これは、私が「アルコール依存」と向き合うことになった実体験です。
出会いは、忙しい日常の中で
私は当時、仕事をこなすので手一杯で、日々疲れていました。
そんなとき、知人から「若くて動ける人材を探している」と相談を受け、地域活動で出会った彼を思い出し連絡しました。
「仕事を変えたいけど、子どももいるから簡単じゃないんです。」
とシングルファザーだった彼に相談されたことがきっかけで交際が始まりました。
最初の印象は、とても素直で明るい人。
仕事で落ち込んでいる私に、彼は家族のよさや温かな言葉をたくさんくれました。
「パパの部屋はお酒がいっぱいある」
違和感の始まりは、彼の子どもの一言でした。
彼は実家暮らしで、私は家に上がったことがありませんでした。
沖縄では、祝い事や集まりでお酒を飲むのは当たり前。
私の周りも“酒飲み”が多かったので、「散らかっているのかな」と深く考えることはありませんでした。
しかし、会うたびに彼からお酒の匂いを感じるようになり、
「今日は飲まないで」と伝えても、彼は何かと理由をつけて飲み続けました。
私の中に少しずつ、モヤモヤとした不安が積もっていきました。
「アルコール依存」で亡くなった同僚
ある日、長期休暇をとっていた会社の上司が亡くなりました。
死因は、アルコール依存症に伴う身体的合併症でした。
私はお通夜の帰りに彼に会う約束をしていたため、
「今日は飲まないでね」と念を押しましたが、
迎えに行いくと、彼からはアルコールの匂いがしました。
約束を破られたこと以上に、「悪びれない態度」に違和感を覚えました。
そして「飲み過ぎだよ」と注意すれば喧嘩になることも増えていきました。
子どもの発作、そして「アルコール依存症」という現実
3人で暮らことになり初めて、彼が毎日お酒を飲んでいた事を知りました。
私は彼に「飲酒運転になる」とか「子どものためにも控えてほしい」など日常的に注意するようになりました。
彼は、しぶしぶお酒を控えると言いましたが、
私が見ていないときや車の中など隠れて飲むようになり、
「飲むな」と言えば逆上したり、飲んでいるのに飲んでいないと嘘をつくようになっていきました。
そんな中、子どもに発作のような症状が現れました。
医師からは「ストレスによるチック症」と診断され、私も彼はショックを受けました。
さすがに彼もお酒を控えるだろうと考えていましたが、
彼は、変わらず理由をつけてお酒を飲み続けました。
私が無理やり飲まない日をつくると
次の日に手が震える等の症状がでたり、常にイライラして、仕事に支障がでてしまうと再び飲みました。
「子どもを大切に思っているはずなのに何かおかしい」
手の震え、嘘、怒り、自己否定。。。
ネットや本で調べていくうちに、
彼は、「アルコール依存症」であることに気づきました。
「合法の薬物」——お酒の正体を知る
「アルコール依存症」は、常にお酒を持って手が震えているような人をイメージしていましたが、
実際は日常的にお酒を飲んでいたり、飲むとセーブできずにいつも飲みすぎてしまう時点で、すでに依存しているということ。
お酒を飲み始めた段階で、誰もが入口には立っていて、急になるのではなく、徐々に蝕まれていくのです。
アルコールは依存性があり、脳や身体、心にも影響を与える「合法の薬物」。そして「否認の病」とも呼ばれます。
本人はアルコールの問題を認めようとせず、「少しくらい平気」と飲酒を正当化し周囲の注意を受け入れません。
彼も飲むことをやめられませんでした。
断酒会や専門医の存在を知り、
必死で説得を続け、
ようやくアルコール依存の専門医がいる「糸満晴明病院」を受診させました。
そこで、「アルコール依存症」と診断されました。
医師は静かに言いました。
「アルコール依存症は、自分の意思ではコントロールできない病気です。」
彼はお酒を控えるため処方された薬を試したましたが、2日で限界が来ました。
離脱症状で手が震え、顔色が悪くなり、怒りっぽくなり、
「もう無理だ」と言って再び飲んでしまったのです。
アルコール依存症は、お酒を口にするとブレーキが効かなくなります。また、禁酒しようとすると、手の震え、発汗、吐き気、イライラなどの離脱症状に襲われ、飲酒欲求が強まります。
さらに飲酒を続けると脳にも悪影響が出て、健康面だけでなく、人間関係や仕事にも深刻な問題が生じていきます。
彼は私に本心を言ってくれてました。
「飲まないと不安で仕方ない。仕事から終わる頃にはお酒を飲むことばかり考えてしまう」
共依存(イネイブラー)というもうひとつの罠
「助けたい」「なんとかしてあげたい」——
その気持ちが、いつの間にか私自身を縛っていました。
共依存とは、依存症者と関わる人が、相手を支えすぎることで自分も壊れていく状態です。
私は彼や子どもの生活を整え、仕事を調整し、
「私が頑張ればよくなる」と信じていました。
しかし、現実は逆で、彼はお酒をやめず、私は精神的・肉体的に追い詰められました。
お酒の問題があると知りながら、酔ったときに介抱したり、迷惑をかけたときに代わりに謝ったりする。
そんなふうに、彼の責任を肩代わりしてしまうこで、反省や問題に気づく機会を奪い、結果的に飲み続けることを可能にしてしまう悪循環が生まれるのです。
家族、友人、同僚、上司など、本人を大切に思っている人ほど、イネイブラーになりやすいのです。
沖縄の酒文化(飲みニケーション)と、見えない依存
沖縄では、祝い事や法事、地域の集まりでお酒が当たり前のように出されます。
「飲まないの?」という言葉が、ごく自然に使われる社会。
そんな環境では、飲酒をやめることが「不自然」とされがちです。
また、未成年のうちから飲酒の機会を経験する人も多く、お酒を飲むことが「普通」になっています。
彼が初めてお酒を飲んだのは未成年だった親戚の集まりだったそうです。
その後、ストレスや孤独、劣等感を紛らわせるように飲み続けるようになりました。
沖縄県だけでなく日本国内ではアルコール依存症の診断者が増加していますが、
実際はその何倍もの「隠れ依存者」がいると言われています。
周囲も、「あの人、よく飲むね」と言いながら、深刻さに気づかない。
依存は誰にでも起こりうる病気なのに、まだ「本人の甘え」と誤解されることが多いのです。
共依存、彼と断ち切る決意
彼は飲み過ぎると自己否定を始め、子どもの前で「俺なんていないほうがいい」と口にすることもありました。
私は彼のストレスを軽減させれば禁酒できると思い、カウンセリングを検討しました。
あるカウンセラーに連絡すると、アルコール依存症の方への対応は専門外と断られましたが、
「あなたのことならカウンセリングできる」と言われました。
最初は、彼や子どもの相談をしようとカウンセリングを受けました。
そこで、「共依存」になっている私自身の状態、仕事のストレス、そして彼との日常で頭が回らなくなっていること、
「彼を救いたい」という思いが、いつの間にか「彼に縛られている」状態になっていたことに気づきました。
カウンセリングに通ううちに、まず転職することを決意しました。
転職前は、「そう言われてもこのままではよくない」「子どもはどうするんだ」と、共依存の感覚から抜け出すことはできませんでしたが、
転職して時間ができると、自分がおかしくなっていたことに気づけるようになりました。
そして、彼の浮気や嘘が続いたとき、
このまま頑張っても私が壊れるだけで、彼のためにもならないと気づき、
別れることを決意しました。
あのまま一緒にいたら、私も彼も共倒れし、子どものためにもならなかったでしょう。それでも、彼の子どものことは心配で胸が痛みます。
アルコール依存症について周りに話すようになると、周囲にも父親や夫のお酒の問題に悩む人が多いことに気づきました。
私は彼と別れて、お酒の恐怖から離れることができました。
今は別の方と結婚し、子どもを授かり、忙しくも穏やかな毎日を送っています。
しかし、断酒会で出会った人や家族、私に悩みを打ち明けてくれた人達は今も苦しみ続けています。
若い世代に伝えたいこと
お酒は、楽しむものでありながら、間違えば人を壊します。
そして、依存は「性格」ではなく「病気」です。
一度はまると、自分の意思では抜け出せない。
だからこそ、まだ未来のある若い世代には、
「お酒のリスク」をきちんと知ってほしいと強く思います。
知識を持つことは、自分だけでなく周囲を守ることにもつながります。
沖縄の温かい文化の中にある「お酒」。
その明るさの裏にある「依存の影」。
について知ることから、私たちの社会は少しずつ変われるのではないでしょうか。
もし、あなたや大切な人が「お酒をやめたい」「飲み方が心配」と感じているなら、一人で抱え込まないでください。
回復の一歩は、「気づくこと」そして、「行動すること」です。
これからの私が伝えていきたいこと
彼と別れてしばらくは体も心も抜け殻のようでした。
共依存を断ち切るというのは、単に相手との関係を終わらせることではなく、
「自分の中の依存」と向き合うことでもあります。
あの頃の私は、彼や子どもを助けたいという思いで自分を見失っていました。
彼が飲むたびに苦しみ、彼が嘘をつくたびに傷つき、
それでも「今度こそやめてくれる」と信じていました。
でも、信じることと依存することは違います。
私自身も、共依存という“もうひとつの依存”の中にいたのです。
沖縄という場所で伝えたいこと
沖縄は、美しい自然と温かい人、おすすめできる所がいっぱいあります。
その一方で、「飲みニケーション」というお酒文化が生活に根づいています。
結婚式、法事、模合(もあい)、職場の飲み会——
どんな場にも泡盛があり、「一緒に飲もう」と勧め合う。
その優しさの裏に“断れない空気”も生まれています。
場では上司から勧められ、飲めない人より飲みすぎる人が喜ばれることもあります。
私が読んだ『禁酒セラピー』という本の中で、
「お酒の本当の味は不味い」と書かれていました。
確かに初めて飲んだときは苦く、ジュースの方が美味しかったのを覚えています。
沖縄の自殺率やDV、児童虐待されている背景にはアルコールの影響も深く浸透していると報告されています。
「みんな飲むから」「うちなータイムだから」と笑いながら、
誰かの心や家庭が静かに壊れていく。
私は、その“見えない痛み”を、見過ごしていると思うと辛いです。
「私たちは待つことしかできない」—あの言葉の意味
専門家の言葉が今でも忘れられません。
「私たちは待つことしかできない」
最初に聞いたときは、絶望のように感じました。
助けたいのに、何もできることがないのかと。
でも今は“待つこと”とは、
「治療は、本人の力(意志)に委ねるしかない」という意味だったと思います。
どんなに支えたいと思っても、
依存症の治療は本人の意志がなければ始まりません。
他人ができるのは、環境を整え、必要な支援につなげ、
そして、距離をとりながら見守ることだけ。
本人に治す気がなければ、無理やり治療してもすぐ元の生活に戻るだけです。
沖縄県立図書館での気づき
アルコール依存症については、沖縄県立図書館で何冊かの本を読み、多くの気づきを得ました。
「アルコール依存症から抜け出す本」と、タイトルは今も思い出せませんが、
依存症と家族関係をテーマにした本を読みました。
ページをめくるたびに、自分の生活の断片が重なって見えました。
「依存症は本人だけの問題ではなく、周囲の環境にも原因がある」
「共依存してしまうパートナーの家庭環境にも問題がある」
う書かれていて、私は深く納得しました。
実は、私の父や祖父も依存症の当事者でした。
父は飲みすぎる以外は真面目に働いていたので、依存症だとは思ったことがありませんでした。
けれど、母に離婚理由を聞くと、お酒のトラブルも関係していました。
私の願いとブログを書いた理由
この経験を通して、私は一つの願いを持つようになりました。
アルコールだけでなく、タバコ、薬物など、社会で禁止・制限されているものには理由があります。
依存は「特別な人」の問題ではなく、誰にでも起こり得ます。
一度依存してしまうと抜け出すのはとても困難で、
抜け出した後も、長い時間をかけて苦しみを乗り越えなければなりません。
だからこそ、未来ある世代、特に未成年の子どもたちに、
「アルコールを含めた依存の怖さやリスク」を正しく伝えたいのです。
そして、今まさに悩んでいる人たちに、
抜け出すきっかけを届けたい——そう思って、今ブログを書いています。
お酒を飲む文化を否定するつもりはありませんが、
その中で苦しんでいる人たちがいることを、もっと知ってほしいです。
同じように苦しんでいる人たちに、
「あなたが壊れる前に助けを求めてほしい」と伝えたい。
依存症は、本人だけでなく、周りの人の心までむしばむ病です。
でも、気づき、学び、つながることで、誰かの人生を守ることができます。
私もまだ完全ではありませんが、沖縄社会に「変わるきっかけ」を届けたいと思います。
最後に——お酒との付き合い方を見つめてほしい
お酒を飲む自由も、飲まない選択も、どちらも尊重される社会であってほしい。
依存の怖さは、「知らないこと」から始まります。
知ることで、救われる人が必ずいます。
今、誰かの飲酒に悩んでいるなら、
一人で考えず、「相談する」という行動を選んでください。
それが回復の始まりです。
私も、共依存しているときは抱えきれず、職場や友人、家族、沢山の人に相談していました。
その時、「別れたほうがいい」「まず自分の体を大切にしないと」等と真剣に話を聞いてくれた人がいました。
カウンセリングが最後のスイッチでしたが、その言葉の積み重ねのおかげで今の私がいます。
人の体を「メガネ」に例えた話に共感して
人の体も心も一つしかありません。
壊れてしまうと、元通りにはなりません。
だからこそ、あなたの心と体を、どうか大切にしてください。
その心と体を守れるのは、あなた自身だけです。
もし今、自分が壊れそうな現状にいるなら、
どうか勇気を出して、人生を取り戻すための一歩を踏み出してほしいです。
📚おすすめの一冊:
『だらしない夫じゃなくて依存症でした』(扶桑社)
依存症を抱える家族の現実を、具体的な体験から描いた一冊。
※沖縄県県立図書館にある。
『新版 アルコール依存症から抜け出す本』(樋口進)
依存症の基礎知識や「若者の集中飲酒」や「減酒治療」の情報が図解付きで説明。
※沖縄県県立図書館にもある。
『マンガでわかる心療内科依存症編(酒・タバコ・薬物)』(ゆうきゆう/少年画報社)
依存症が脳や心理にどんな影響を与えるか、飲酒や喫煙などの具体例をわかりやすく説明。
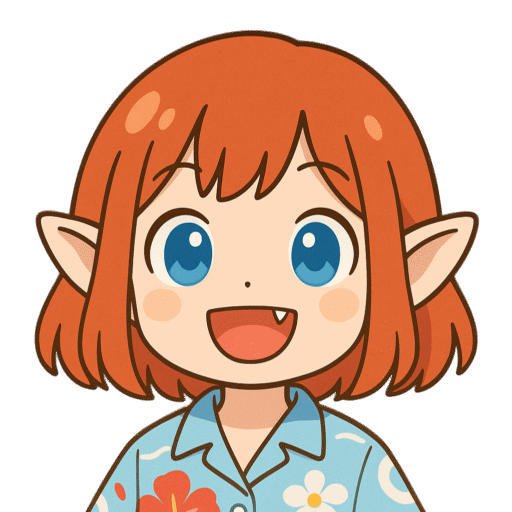

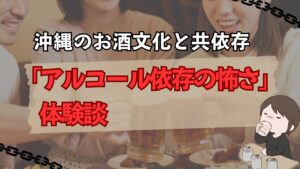
コメント