 なびんちゅ
なびんちゅこの記事をみた方の中には、「ないちゃー」と呼ばれて、なんだか嫌だなとモヤモヤした気持ちになったことがある方もいると思います。
実は沖縄で使われる「ないちゃー」という言葉の背景には歴史や地域意識が影響しています。
ここでは、「ないちゃー」や「うちなーんちゅ」、「寄留民(きりゅうみん)」といった言葉が、
- どのような意味をもって使われているのか、
- 気をつけておきたいポイント、
- そこに込められた沖縄独特の地元意識について、
私自身の体験も交えながらお話ししたいと思います。
沖縄の生活や文化に興味がある方はもちろん、これから沖縄に移住しようと考えている方、あるいは沖縄出身の人と日常的なお付き合いのある方にも、少しでも参考になる内容をお届けできれば幸いです。
1. 「うちなーんちゅ」と「ないちゃー」とは
「うちなーんちゅ」とは、沖縄生まれの人々を指す言葉です。
この言葉は沖縄の方言に由来しており「うちな」は沖縄を意味し、「ちゅ」は人を表します。
一方で、「沖縄以外の地域」から来た人は「ないちゃー」と呼ばれることがあります。
「本土の人」「県外の人」と言いたいときにも、「ないちゃー」と表現されることがあるため、耳にしたことがある方も多いでしょう。
この「ないちゃー」という言葉は、言う人・言われる人によって感じ方がまったく違います。
昔から使われてい地元の人にとっては「あいさつ程度」「相手にフランクに話しかけるための言い方」という認識もあれば、呼ばれた本人にとっては「区別されている気がする」「差別に近い響きを感じる」など、場合によってはネガティブな印象を持たれることがあります。
沖縄の人は、地元愛や地元意識が強い方が多く、これは、よい面も悪い面あると思っています。
特に沖縄の人々は独自のアイデンティティを自然と育んでいて、「うちなーんちゅ」としての自負心が強い方が多い一方で、他府県から来た人を「ないちゃー」と呼ぶことで、一種の「仲間外れ」感を生み出してしまうことがあります。
「うちなーんちゅ」と「ないちゃー」という言葉は、沖縄独自の歴史や文化、地域意識から生まれた表現であり、使われる場面や人によってニュアンスが異なるのが特徴です。
2. 私が「ないちゃーか?」と聞かれた体験
私自身は、生まれも育ちも沖縄です。
いわゆる「うちなーんちゅ」に分類されますが、名字が沖縄本島内になく、学生の頃はよく「ないちゃーなの?」と聞かれることがありました。
私の家系は「曽祖父が県外の離島出身で、祖父の代からずっと沖縄に住んでいる」という状況だったのですが、それを説明しても「じゃあ、ないちゃーだね」と言われてしまう経験がありました。
 なびんちゅ
なびんちゅ子どものころは純粋に
「なんで?私は沖縄でずっと暮らしているのに。」と不思議に思いましたし、どこか傷つく気持ちもありました。
見た目や言葉がどうこうではなく、名字だけで「ないちゃー」扱いされるのは寂しかったのです。
ですが、社会に出てからは、むしろ珍しい名字のおかげで
「すぐに名前を覚えてもらえるし、話のネタになるからいっか」
と考え方を切り替えられるようになりました。
こうした体験は人によって大きく差があります。
私は気持ちを切り替えることができましたが、「なかなか割り切れない」「呼ばれるたびに疎外感を覚える」という人もいると思います。
単に地域の違いを表すための言葉でも、「ないちゃー」と言われることで心がチクっと痛む人がいるのも事実なのです。
3. 「ないちゃー」の使い方と地域の人の思い
私は社会人になって県内の様々な地域で年配の人と交流する機会が増え、
「ないちゃー」という言葉を発する側には、悪気なく「相手と打ち解けたい」「話しかけるきっかけを作りたい」という意図で使っている人も多い印象をもつようになりました。
特に年配の方などは「ないちゃー」という言い方そのものが当たり前で、「差別的なニュアンスを含んでいる」とすら意識していない場合もあるのです。
実際、私が地域の人と交流するイベントに参加したとき、ある70代の方が「どこから来たの?ないちゃーねぇ?」という具合に、声掛けのきっかけとして使っていました。言われた当人がどう感じるかはケースバイケースですが、少なくとも「悪意や敵意を込めてはいない」ということは分かりました。
表現としてはストレートすぎるかもしれませんが、初対面で出身地や名前を聞く流れで、「ないちゃーは話題にしやすい」といった感じで、挨拶程度に言われることが多かったです。
4. 沖縄の歴史と戦後差別の名残り
沖縄には、長い歴史の中で戦争や戦後に差別が存在しました。
年配の方々の中には、本土(他府県)から受けた差別的な態度を直接経験したり、親からその話を聞かされながら育った人もいます。
こうした苦い思いを抱えている人たちは、時に「ないちゃー」という言葉を、嫌味や批判の意図を込めて使うこともあります。
たとえば、戦後沖縄が米軍統治下にあった時代、
本土側から「沖縄は遅れている、日本人ではない」といった侮蔑を受けたり、旅行先や進学先で差別的な扱いを受けた人たちは、その体験を心に抱え続けて生きてきました。
そうした経験が染みついているために「どうせあっち(本土)は…」という偏見を持ってしまい、県外の人を「ないちゃー」と呼び、距離をとってしまう人もいるようです。
しかし、どこで暮らしていても同じことが言えます。親切な人もいれば意地悪な人もいます。これは沖縄と本土に限らず、国籍や人種の違いにもいえます。
大切なのは、
過去の差別体験にとらわれ「相手をひとくくりに嫌う」のではなく、個々の人とのコミュニケーションを大事にする意識だと思います。
交流を重ねていけば、いつも野菜をくれたり、仲間として迎え入れてくれる人もいっぱいいます。
 なびんちゅ
なびんちゅ沖縄の歴史や文化の中で育まれた感情や経験は、今でも人々の心に影響を与えています。理解し合うためには、過去の痛みを認識しつつ、未来に向けて新たな関係を築いていくことが大切だと思います。
5.「寄留民(きりゅうみん)」という考え方
沖縄では、昔から集落ごとのつながりや地元意識が強く、外部の人を「寄留民(きりゅうみん)」と呼ぶ独特の距離感が存在します。
この「寄留民」という言葉は、
単に「他県から来た人」だけを指すのではありません。
たとえば、同じ沖縄県内でも別の島や地域から移り住んできた人や、結婚して他所から嫁いできた女性のことも「寄留民」と呼ぶことがあります。
私が驚いたのは、とある地域の聞き取りをしていたとき、80代の女性が「私は寄留民だから……」と口にしたことです。その方は、50年以上もその土地に住んでいるのに、いまだに自分を「よそ者」と感じているのかと思いました。
 なびんちゅ
なびんちゅ「もう半世紀もそこに住んでいるのに?」
と驚きましたが、それはご本人にとっては、どこか「地元の人と全く同じ」にはなれないという思いがあるのかもしれません。
これが良い悪いではなく、地域に根付いた伝統的な意識なのでしょう。
那覇や都市部では、こうした「寄留民」という言葉を耳にする機会はほとんどないかもしれません。しかし、昔からの集落の文化や自治会のつながりが色濃く残っている地域では、今でもこうした感覚を持っている人もいます。
私は子ども時代に引っ越した先の地域の同級生に言われたことがあり、初めは嫌な気持ちになりました。
ですが、住んで50年の人でも口にする言葉と知ったことで、
もし言われても、自分だけでなく、多くの仲間(寄留民と言われる人)がいるんだ!!と思ってほしいってことです。
 なびんちゅ
なびんちゅ「ないちゃー」という言葉と同様に、悪気なく使う人も多いので、
「地元意識強い人だな」と深い意味にとらえないことをオススメします。
「寄留民(キリューミン)」とは、もともと明治維新以前から、故郷や本籍地を離れて他の土地に移り住み、そこで定着した人々やその子孫を指す言葉でした。最初の移住から何世代経っても「よそ者」と見なされることが多く、地域社会の中で独特の立ち位置を持っています。
今では、他県や県内の別の地域から移り住んだ人や、嫁いできた女性なども広く「寄留民」と呼ばれています。たとえ長年その土地で暮らしていても、「よそ者」としてのニュアンスが残るのが特徴です。
6. 沖縄の地元意識:助け合いと疎外感
沖縄の地元意識は、よい面と悪い面があります。
よい面としては、「ゆいまーる」と呼ばれる助け合いの精神や、地域行事や伝統を大切にしようとする姿勢が挙げられます。
たとえば老人クラブや自治会が主体となり、
集落全体で子どもを見守ったり、お年寄りと若い世代の交流行事を行ったりします。
移住してきた人たちの中には、こうした温かいコミュニティ関係に救われたり、子育てのしやすさを実感したという声も少なくありません。
一方で、地元意識が強すぎる場合、外部から来た人への偏見や疎外感を生むことにつながりやすいのも事実です。
「ないちゃー」と呼ぶことで「あなたは私たちと違う人」という線を引く感覚が生まれたり、「寄留民」として常に“外”の立ち位置から見られてしまうこともあります。
もちろん、すべての地域でそうだというわけではありませんし、人によっても態度や考え方は違います。
7.「ないちゃー」や「外人」と呼ばないようにする意識
私が学生時代に「ないちゃー扱い」を受けて嫌な思いをしたこともあり、いまは自分が相手に対して「ないちゃー」と呼ぶことがないように気をつけています。
それは、単純に
「言われたら嫌な思いをする人がいるのなら避けよう」と考えるからです。
また、海外の方に「外人(がいじん)」と呼ばないようにも注意しています。
「外国の人を指す当たり前の言葉」として使わう人もいるかもしれませんが、「外」と「内」で区切る差別的な表現に捉えられる可能性が高いです。
特に国際交流の多い沖縄では、海外からの観光客や在住者、国際結婚で家族がいる人も多いため、差別された感じてしまう表現は避けることが大切だと思っています。
8. 移住者と沖縄の文化・行事
地元意識が強い沖縄では、伝統行事や地域のイベントを盛り上げようとする心が根付いています。
エイサーの練習やお祭り、地域の運動会などに力を入れている地域も多いですが、これを「うるさい」「迷惑」と否定する移住者も一部にはいます。
もちろん、法律や条例を超えた大きな音量が長時間続くのであれば改善が必要ですが、
「自分には関係がない、興味がないからやめてほしい」という一方的な要求の仕方は、地元の人々の強い反発を招く原因になります。
結果として「ないちゃーがわがまま言っている」という負の感情が生まれ、薄れかけていた差別意識が再燃してしまうことも考えられるでしょう。
また、「沖縄の人は〇〇だから」などと、限られた体験だけで沖縄の人たちをひとくくりにして批判する人もいらっしゃいます。
これも、沖縄の人たちが「どうせないちゃーは……」と思ってしまう負の連鎖を生む恐れがあります。
互いに「ひとまとめに見て批判し合う」関係性は、せっかくの楽しい交流を遠ざけるだけです。
9. 沖縄で出会う人々のやさしさと厳しさ
実際、私が体験してきた沖縄のコミュニティの多くは、温かい人々に囲まれていました。
地元の野菜や果物を「食べきれないから持っていきなさい」とくれる人、行事の準備や片付けを積極的に手伝ってくれる人など、昔ながらの「ゆいまーる」を大切にしている方が多いのです。
確かに「うちなーんちゅ」に対して強いプライドをもっている人は多いですが、そこには「共同体を守りたい」「みんなで支え合いたい」という想いも含まれています。
自分自身が過去に差別を受けたことから「今度は自分が区別する側になろう」と意識せずにしてしまう人もいます。
そうした人をどう受けとめ、どう対応するかは、個人の人間関係次第かもしれません。
しかし、コミュニケーションを重ね、誠意を持って接していくことで、徐々に打ち解けていくケースも多々あります。
10. 漫画「ONE PIECE」に見る沖縄の差別と記憶
自分が他県出身であれ、沖縄出身であれ、相手をどのように考え、どう接するかは一人ひとりの心がけ次第だと思います。
ここで、私が特に印象深かったのは、人気漫画『ONE PIECE』の63巻に登場する言葉です。
魚人島「タイヨウの海賊団」を率いたフィッシャー・タイガーが、奴隷にされた悲劇を背負いながらこう言います。
「誰でも平和がいいに決まってる!
だが、本当に島(魚人島)を変えられるのはコアラのような何も知らねェ次の世代だ。
だから頼む! お前らは島には何も伝えるな。おれ達に起きた悲劇を…おれ達の怒りを!!」
このセリフを初めて読んだとき、心にぐっとくるものがあり、
タイガーの「自分たちの受けた差別や苦しみを、そのまま次の世代に背負わせない」という決意を感じました。
そんなセリフに私も、本土と沖縄の間にも、歴史的経緯から生じた差別感やわだかまりがありますが、その怒りの感情を子どもたちに受け継がせないことが大切ではないか、と強く感じたのです。
差別につながる嫌な記憶が残っても、それを他の人にしない。子どもたちに伝えないことが大切だと思いました。
11. 嫌な思い出を次世代に押しつけないために
私自身、「ないちゃー」と呼ばれて疎外感を覚えたと思う瞬間が、振り返れば何度もありました。
ですが、同時に考えたいのは、「自分が嫌な思いをしたなら、今度は自分がその言葉を使わないようにしよう」ということです。
もし相手が不快に思うかもしれないと分かっている表現ならば、違う言い方を選びたい。
実際、沖縄には独特の表現がたくさんあり、それを楽しく共有し合う方がずっと建設的だと感じます。
また、自分が過去にされたことを、次の人に繰り返すことはやめようと思います。
嫌だった記憶や、差別的に扱われた気持ちを子どもや後輩に語るときには、「こういう経験があった、辛かった。だからこそ、相手を傷つけない言葉遣いを大事にしたいんだよね」という、前向きな方向に変換して伝えるように心がけています。
12. 「うちなーんちゅ」「ないちゃー」「きりゅうみん」のまとめ
沖縄では「うちなーんちゅ」と「ないちゃー」という言葉が長く使われてきましたが、単に県内・県外の区別を表すだけでなく、沖縄独自の歴史や地域意識、そして過去の複雑な経験が反映された言葉でもあります。
また、県内でも「寄留民(きりゅうみん)」という考え方が今も残っており、集落ごとに外部の人との距離感をどう築いてきたのかという沖縄の背景を感じます。
「うちなーんちゅ」「ないちゃー」といった言葉は、悪気なく「あいさつ代わりに使う」という場合もあれば、「疎外や差別をほのめかす」ように受け取る人もいます。
言葉は使う人と受け取る人の関係性や背景によって、そのニュアンスは大きく違います。
だからこそ、相手が不快に感じそうなときや、自分が言われて嫌だった言葉は使わないようにしたり、相手の気持ちを聞いてみたりすることが大切だと思います。
– 地元を大切に思う気持ちはいいことだけど、それが強すぎると他者を遠ざけてしまうことがある
– 何気ない言葉でも相手を傷つけることがあるからこそ、思いやりをもって接することが大切
– 自分が受けた辛い経験や差別を次世代に受け継がせないために、嫌な言葉や態度は自分から断ち切りたい
日々の暮らしの中で、沖縄と他の地域の文化がチャンプルーしながら(混ざり合いながら)、新しい沖縄が生まれ続けているのを感じます。
移住者も、昔からの住民も、お互いを知り合い、尊重し合うことで、より豊かなコミュニティが育まれていくのではないでしょうか。
私自身も、過去のつらい経験を前向きな力に変えて、「誰かを排除しない、傷つけない関係づくり」を心がけたいと思います。
最後まで読んでくれて、ありがとうございました。
 なびんちゅ
なびんちゅもし「ないちゃー」という言葉に違和感を覚えたことがある方は、「必ずしも意地悪な意味ばかりではない」ということも、少しだけ心に留めてみてください。
逆に自分が口にする立場であれば、相手がどう感じるかを気にしながら接してみると、より良いコミュニケーションにつながるはずです。
お互いに歩み寄ることで、沖縄での暮らしがもっと楽しくなることを願っています。
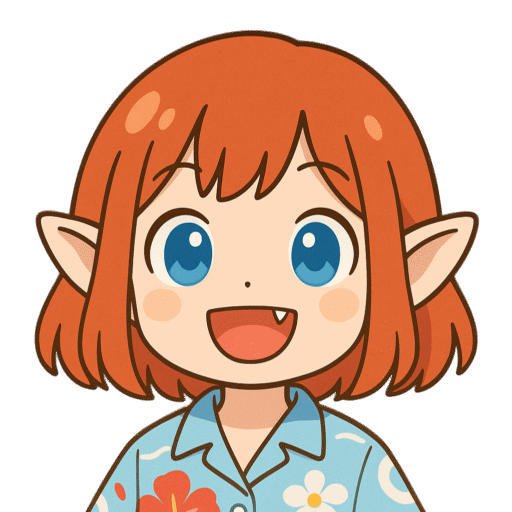
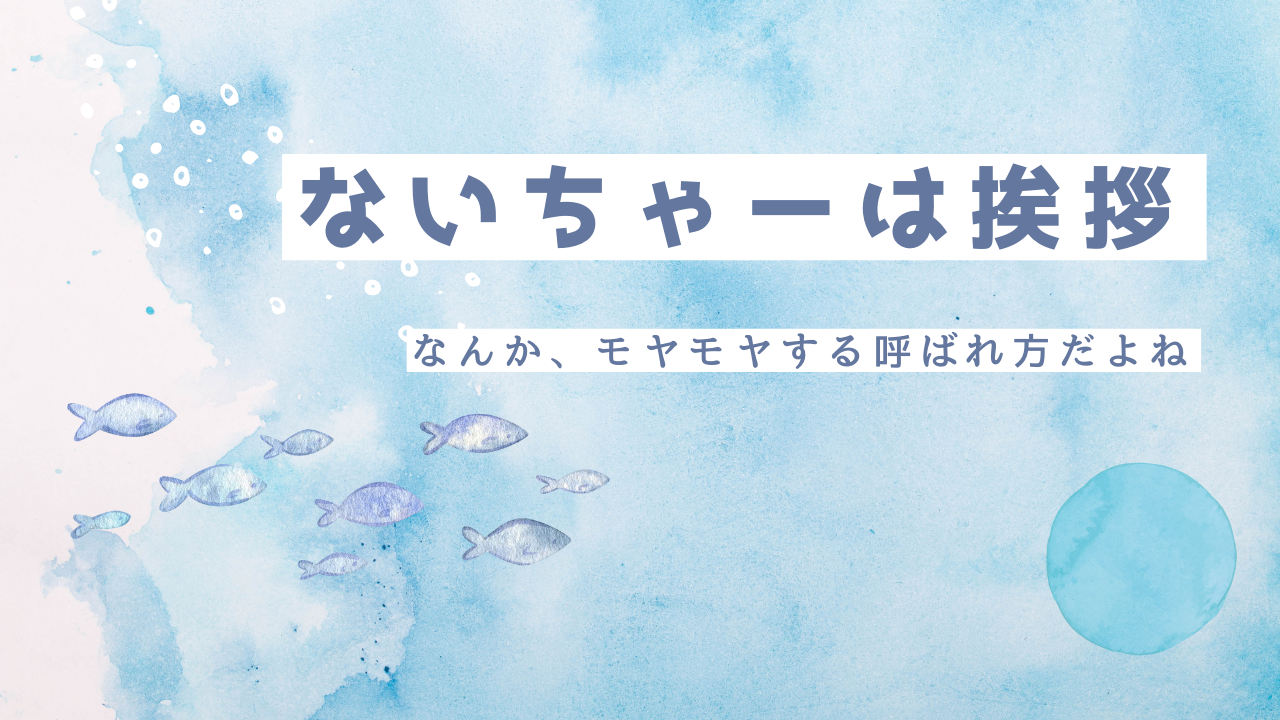
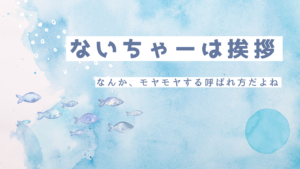
コメント